質問:人は何故祈ったり願ったりするの?叶うはずがないのに。
現代においても、多くの人が神社仏閣で手を合わせ、困った時に「お願い」をします。「どうせ叶わない」と頭では分かっていても、なぜ人は祈り続けるのでしょうか。この人類普遍の謎について、異なる文化圏から選ばれた3人の叡智に学んでみましょう。古代ローマの皇帝哲学者マルクス・アウレリウス、東洋思想の巨人である老子、そして現代心理学の父アドラーが、それぞれの視点から人間の祈りの本質に迫ります。
マルクス・アウレリウスの回答:ストア派皇帝が語る「祈りの真の目的」
 アウレリウス
アウレリウス祈りとは何か?多くの者が勘違いしておる。祈りとは神々に物乞いをすることではない。
私は皇帝として数々の戦いを経験し、疫病に見舞われた民を見てきた。その中で気づいたのは、人が祈る時、実は二つのことが同時に起こっているということだ。一つは外的な願望の表明、もう一つは内的な心の整理である。
私の『自省録』にも記したが、「変えられるものと変えられないものを区別せよ」。祈りの真の価値は、この区別を明確にすることにある。雨乞いをしても雨は降らぬかもしれぬが、祈ることで人は「自分にできることとできないことの境界」を理解する。これこそが祈りの本質的な効用なのだ。
戦場で部下たちが戦勝を祈る姿を見て私は悟った。彼らは勝利そのものよりも、「最善を尽くす覚悟」を神々に誓っているのだと。祈りとは外的な結果を変える呪文ではなく、内的な意志を固める儀式なのである。
だからこそ私は毎朝、宇宙の摂理に感謝を捧げる。叶えてもらうためではなく、今日という日に最善を尽くす決意を新たにするためにな。「今日という日は二度と来ない」のだから。
老子の回答:道教の祖が説く「無為自然の祈り」
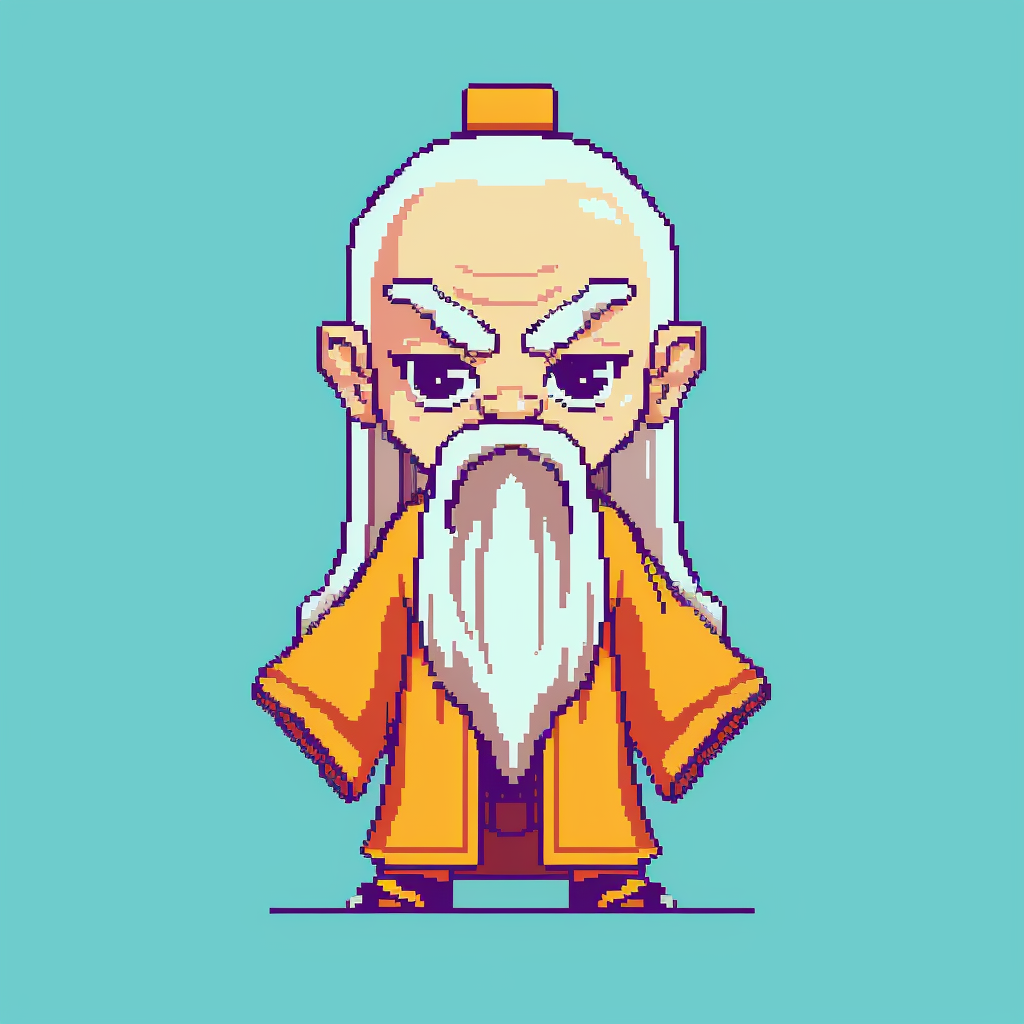
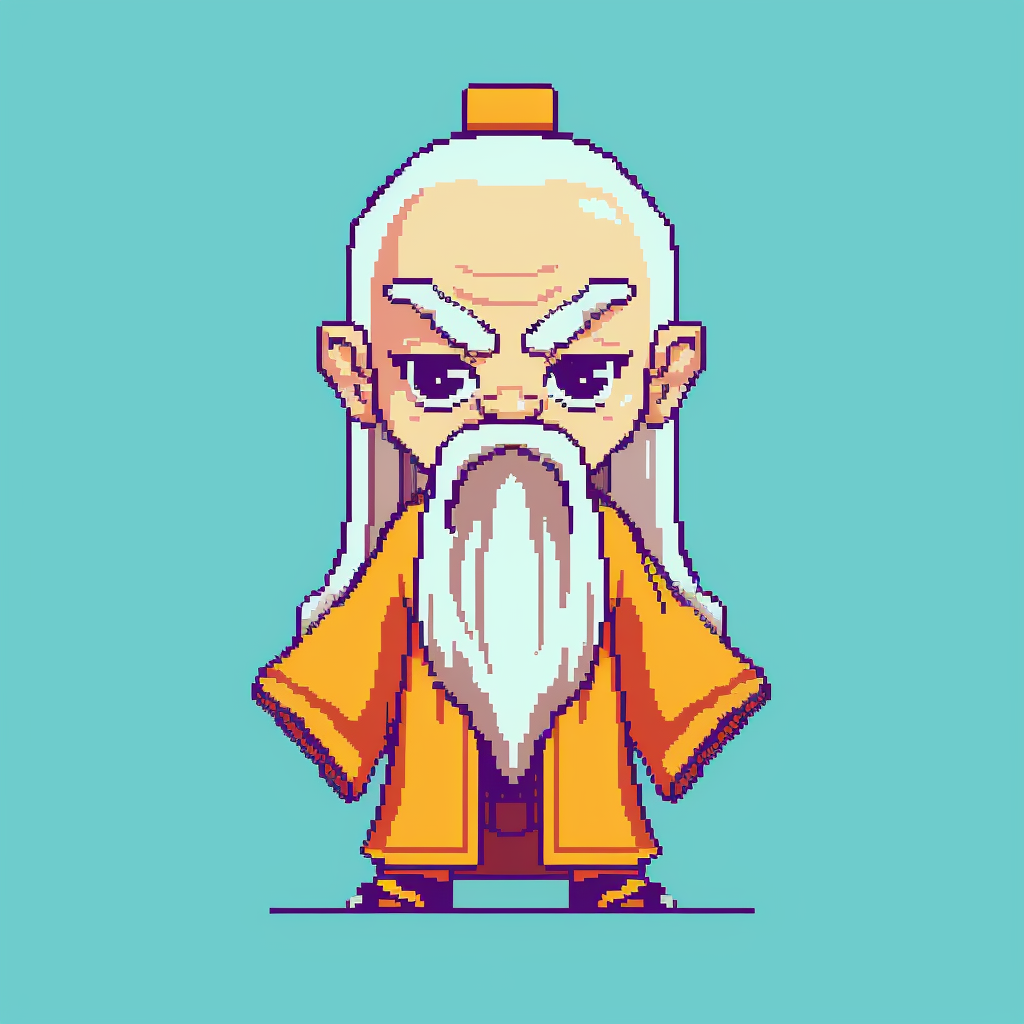
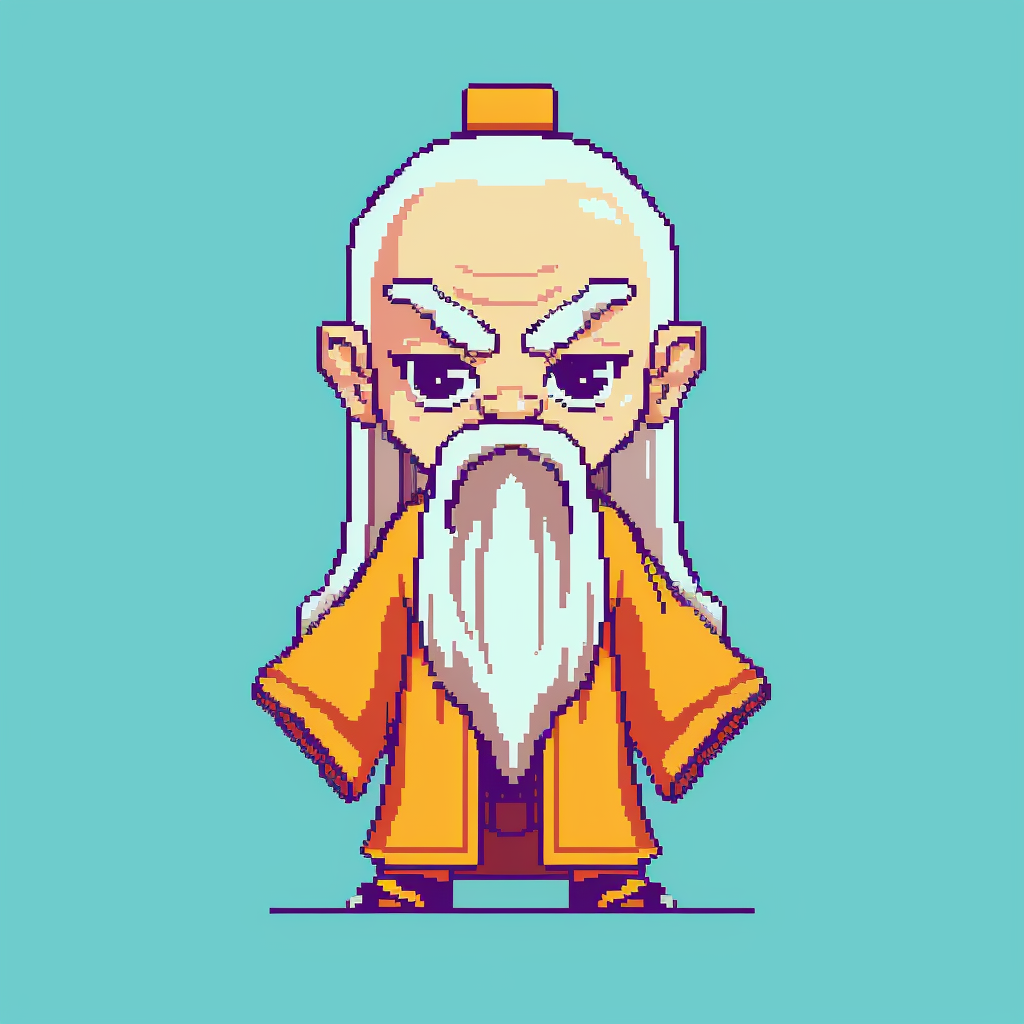
ほほう、叶わぬ願いになぜ祈るかじゃと?それこそが人間の愛おしいところじゃのう。
私は長年、自然の中で瞑想し、水の流れを観察してきた。水は決して山に向かって「どけ」とは言わぬ。ただ静かに流れ、やがて山をも削り取る。人の祈りも同じようなものじゃ。
祈りとは、実は「あきらめ」の別の表現なのじゃよ。「もう自分の力では無理です」と認めることから始まる。これが実は大変重要でな。現代人は何でも自分の意志でコントロールしようとするが、それこそが苦しみの根源じゃ。
私が説く「無為自然」とは、何もしないことではない。自然の流れに逆らわず、でも必要な時には適切に行動することじゃ。祈りは、この自然のリズムに自分を合わせる練習なのじゃな。
雨が降らぬ時、農夫は雨乞いをする。しかし本当に賢い農夫は、祈りながらも灌漑の工夫を怠らぬ。これが「柔よく剛を制す」の実践じゃ。祈りによって心を空にし、そこに新しい知恵が宿るのを待つ。叶うか叶わぬかは宇宙の意志に任せ、自分は今できることを淡々と行う。
祈りとは、人間が宇宙との対話を学ぶ最初の一歩なのじゃよ。
アドラーの回答:個人心理学の視点から解き明かす「祈りの心理的機能」



なるほど、興味深い質問ですね。私の個人心理学の観点から申し上げると、祈りは人間の「共同体感覚」と深く関わっています。
私は長年、人間の行動には必ず目的があると主張してきました。祈りも例外ではありません。表面的には「願いを叶えてもらう」ことが目的に見えますが、真の目的は別のところにあるのです。
第一に、祈りは「所属感」を生み出します。神や宇宙という大きな存在とのつながりを感じることで、人は孤独感から解放されます。これは人間の基本的欲求である「共同体への所属」を満たす行為なのです。
第二に、祈りは「劣等感の建設的な処理」を可能にします。「自分一人では無力だ」という劣等感を、「大いなる力に委ねる」という形で昇華させるのです。これは心理的に非常に健康的な対処法です。
第三に、祈りは「勇気」を与えます。私がよく言うように、「劣等感は成長の源」です。祈ることで人は、困難な状況でも前進する勇気を得られるのです。
興味深いことに、願いが叶わなくても祈り続ける人は、実は無意識的に「祈ること自体の価値」を理解しているのです。祈りによって得られる心の平安、希望、そして行動への勇気こそが、真の報酬なのですよ。
人生に意味を与えるのは自分自身です。祈りは、その意味づくりの重要な道具の一つなのです。
まとめ
三人の偉人が示したように、祈りの価値は「願いが叶うかどうか」にあるのではありません。心の整理を行い(マルクス・アウレリウス)、自然との調和を学び(老子)、共同体感覚を育む(アドラー)という、人間の成長に欠かせない機能を果たしているのです。叶わない願いに込められた人間の叡智を、現代を生きる私たちも大切にしていきたいものです。
