質問:今夫婦別姓が話題となっているが、同姓と別姓、どちらが良いのか?
現代日本で熱い議論が交わされている夫婦別姓制度について、多くの方が悩んでいるのではないでしょうか。「伝統を大切にしたい」「でも個人の自由も尊重したい」と、どちらの気持ちもよく分かります。そんな複雑な思いを抱える皆さんとともに、歴史の偉人たちの叡智を通じてこの問題を考えてみたいと思います。今回は、明治の啓蒙思想家・福沢諭吉、儒教の祖・孔子、そして現代フェミニズムの母・ボーヴォワールの思想から、それぞれ異なる視点での洞察を探ってみましょう。時代も文化も異なる三人の知恵が、現代の私たちにどんな気づきをもたらしてくれるでしょうか。
福沢諭吉の回答:「独立自尊」こそが夫婦関係の基盤
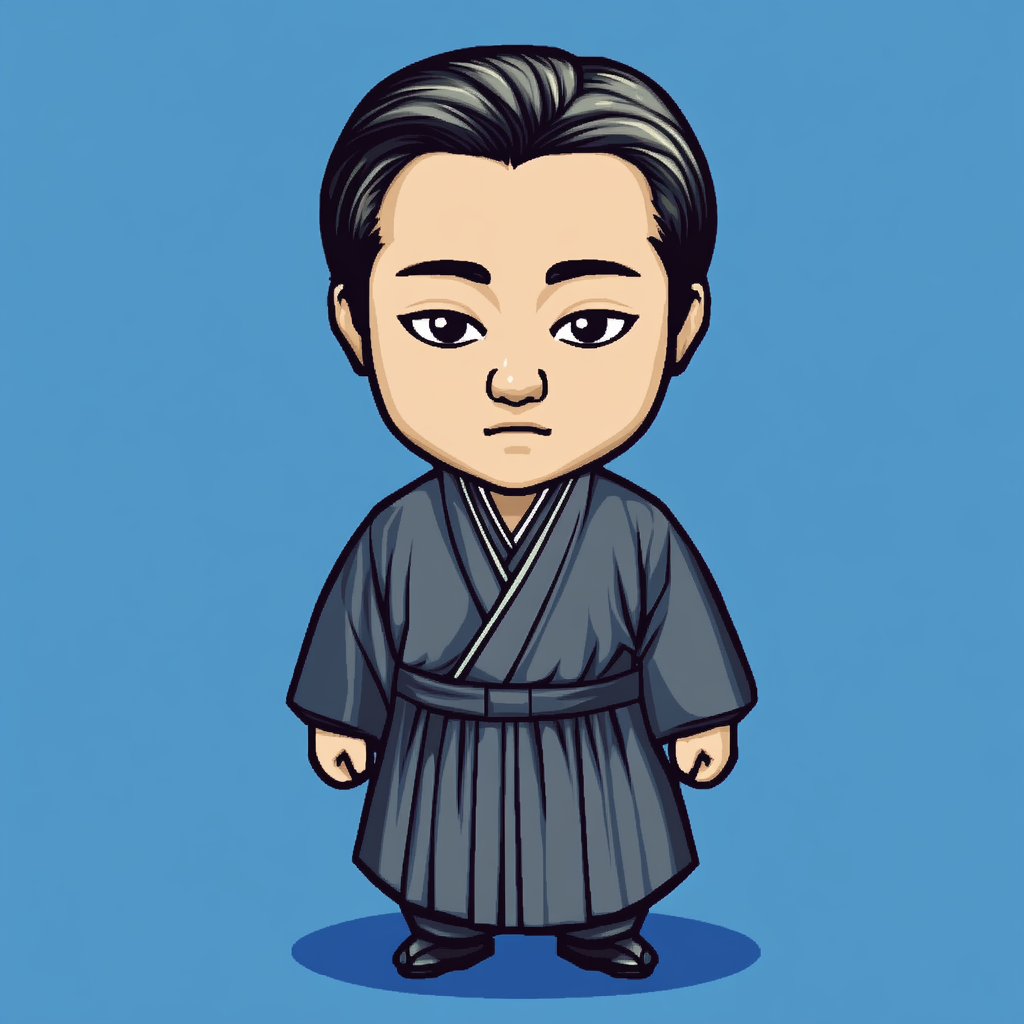 福沢諭吉
福沢諭吉「学問せよ!この夫婦別姓問題こそ、まさに『独立自尊』の精神が問われる場面である」
私が『学問のすゝめ』で説いた「天は人の上に人を造らず、人の下に人を造らず」という理念は、男女の関係においても当てはまる。夫婦別姓反対派が「家族の絆が薄れる」と心配するのは分かるが、それは表面的な形式論に過ぎない。
明治時代、私は女性の地位向上を強く主張した。「男女同権」「女子教育の必要性」を説き、女性も一個の独立した人格として尊重されるべきだと考えていた。姓名とは、その人のアイデンティティそのものである。結婚によって一方的に姓を変えることを強制するのは、個人の尊厳を軽視する行為だ。
私の時代でも、商家の娘が婿養子を迎える際は、男性が女性の家の姓を名乗ることがあった。つまり、姓の変更は決して「女性だけの問題」ではない。重要なのは、双方が納得して選択できる制度を作ることである。
現代の皆さんに伝えたいのは、「独立自尊」の精神だ。お互いが自立した個人として尊重し合える関係こそが、真の夫婦の絆を生む。形式的な「同姓」にこだわるより、精神的な「同心」を大切にすべきではないか。
孔子の回答:「仁義礼智」に基づく家族制度の意義



「仁義礼智の教えによれば、家族とは社会の最小単位であり、秩序の根本でございます」
夫婦別姓の議論を聞いていると、現代人は「個人の権利」ばかりを重視し、「家族の調和」を軽視しているように思える。私が説いた「修身・斉家・治国・平天下」の教えでは、まず個人を修め、次に家族を整えることが、社会全体の安定につながるとしている。
同姓制度には深い意味がある。夫婦が同じ姓を名乗ることで、一つの家族としての結束が生まれ、子どもたちにも安定した帰属意識が育まれる。これは単なる形式ではなく、「礼」の精神に基づいた社会制度なのだ。
私の時代の中国では、家族の姓は祖先から受け継がれる神聖なものとされていた。しかし、現代日本の状況を見ると、必ずしも男性の姓を選ぶ必要はないと考える。重要なのは、夫婦が話し合い、どちらか一方の姓を選んで家族の統一を図ることだ。
「温故知新」の精神で言えば、古い制度の良さを理解しつつ、現代に合わせて柔軟に適応することが大切である。ただし、選択制を導入する際は、家族の絆が弱まらないよう、社会全体で支える仕組みも必要だろう。
夫婦別姓を選ぶカップルには、子どもの姓をどうするか、家族としての一体感をどう保つかなど、より深い話し合いが求められる。「仁」の心、すなわち相手を思いやる心を持って、共に答えを見つけてほしい。
ボーヴォワールの回答:「第二の性」からの解放
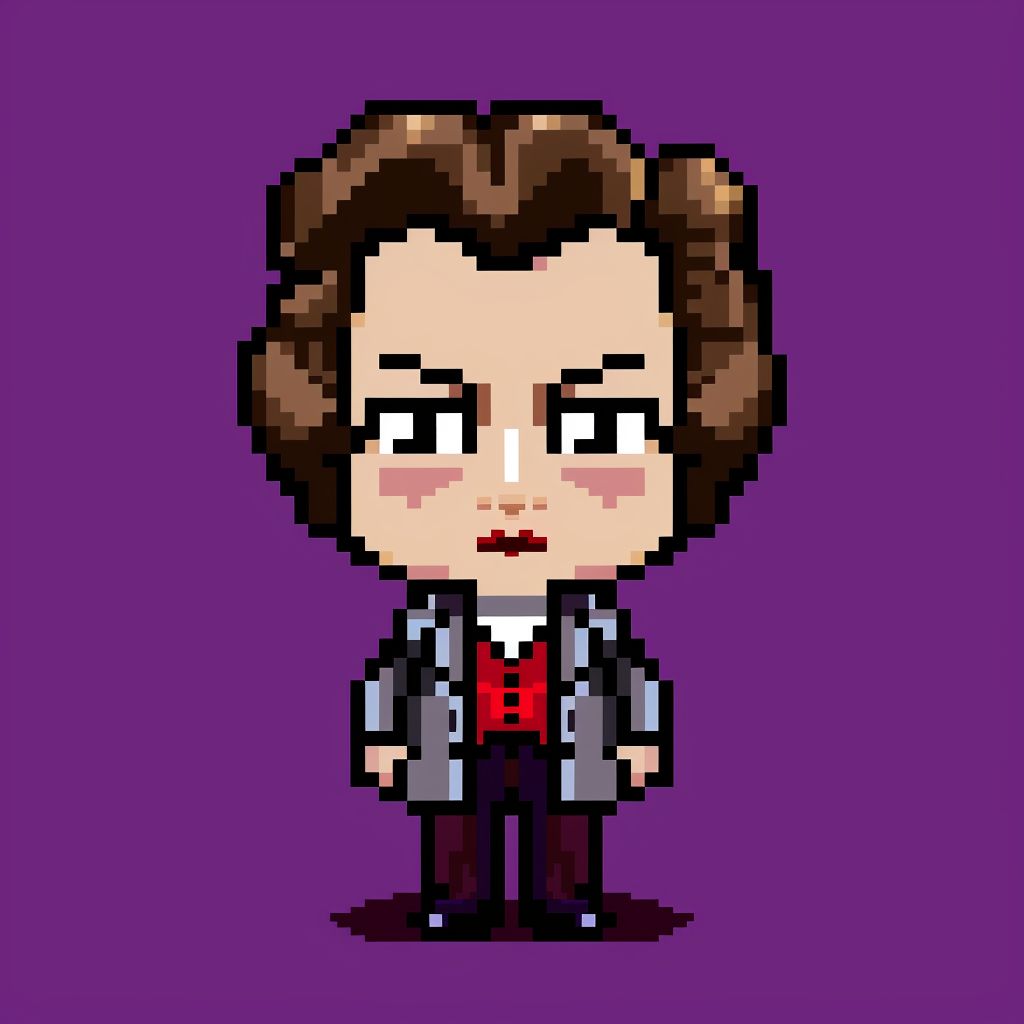
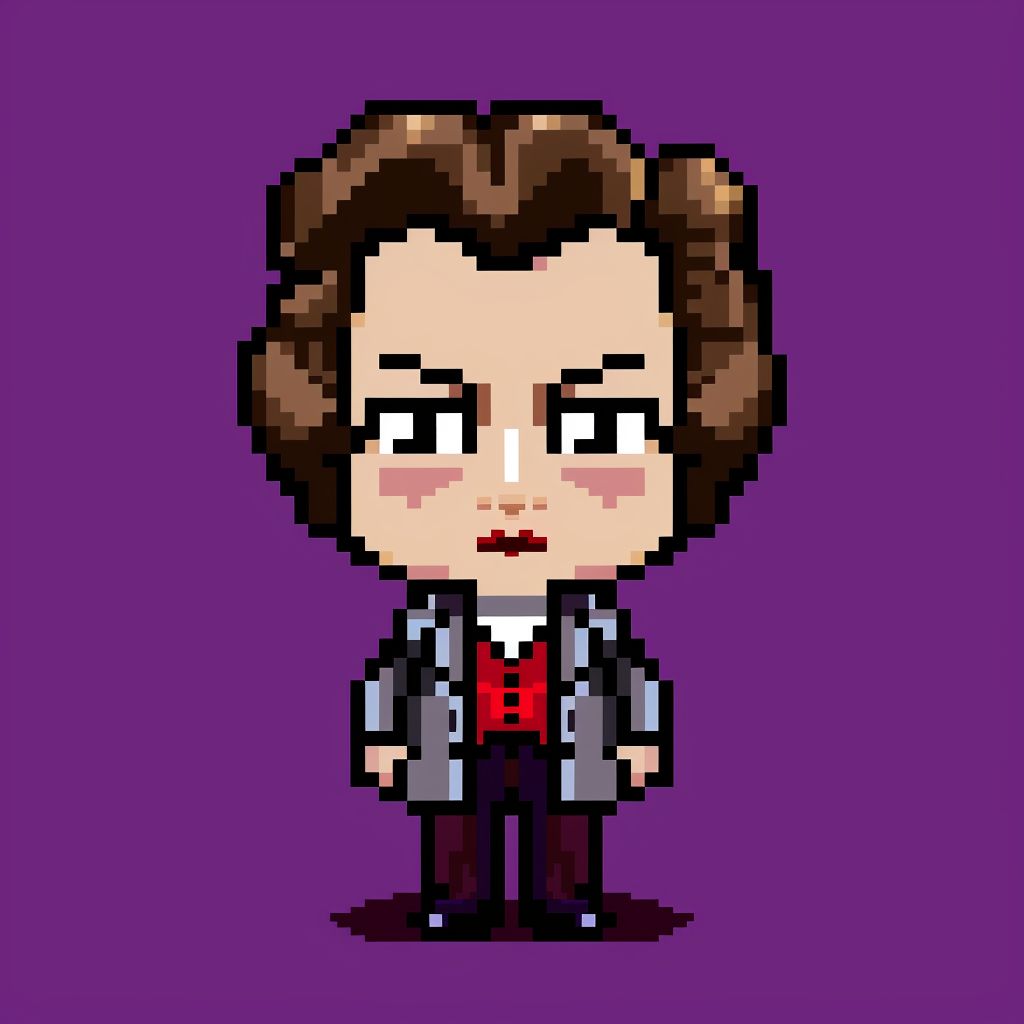
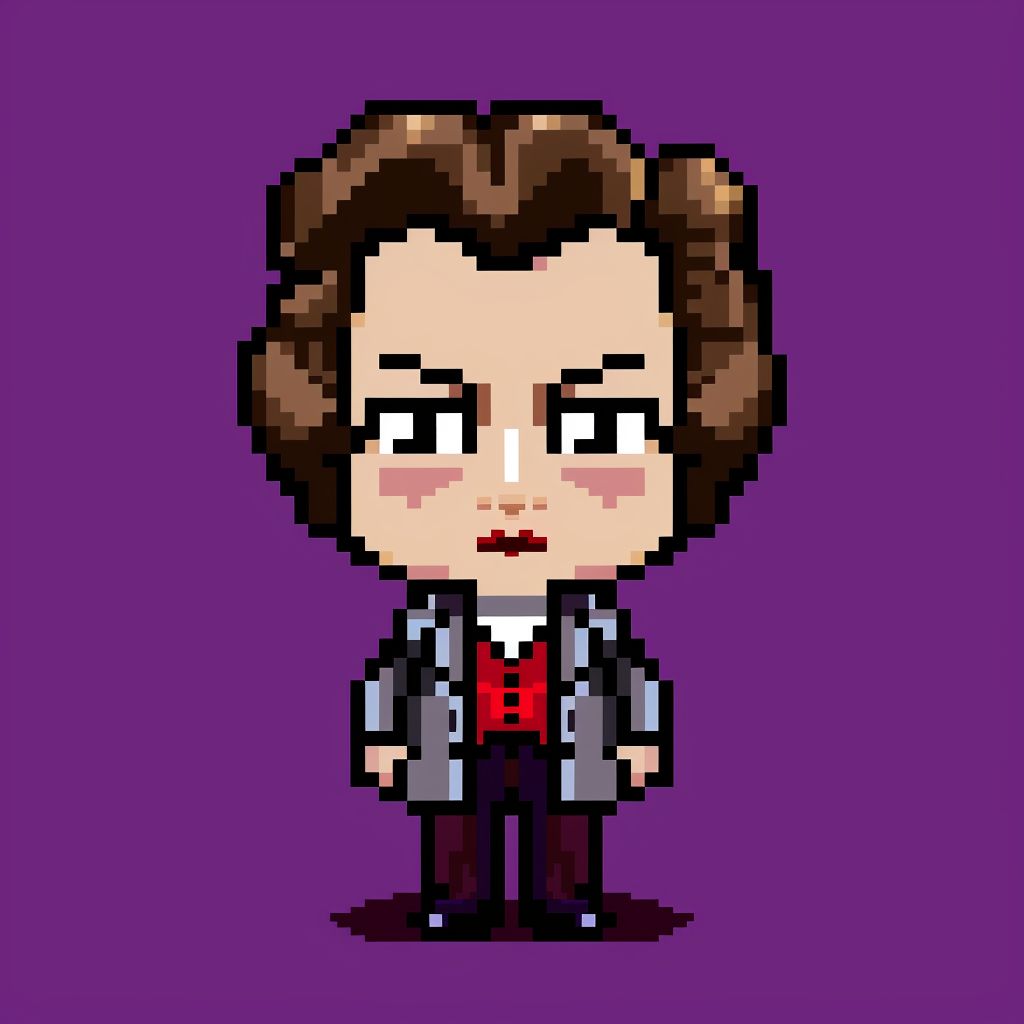
「人は女に生まれない、女になるのよ。そして、『妻』という役割に押し込められる必要もないの」
夫婦別姓問題は、まさに私が『第二の性』で指摘した「女性の従属性」の典型例だわ。なぜ結婚すると、圧倒的に女性が姓を変えなければならないの?これは明らかに男性中心社会の産物よ。
私が生きた20世紀前半のフランスでも、女性は結婚と共に多くのものを失っていた。自分の姓、職業上のアイデンティティ、時には経済的独立まで。「良い妻」「良い母」になることが女性の幸せだと押し付けられていたけれど、それは男性に都合の良い神話に過ぎない。
現代の日本女性を見ていると、高い教育を受け、キャリアを積んでいる人が多い。それなのに、なぜ結婚という契約によって、築き上げてきたアイデンティティを放棄しなければならないの?職場での名前の変更、資格証明書の書き換え、これらは単なる「手続き」ではなく、女性の社会的存在を「リセット」することなのよ。
サルトルと私の関係を例に挙げれば、私たちは生涯にわたって事実婚を選択し、お互いの独立性を尊重した。それによって、真の対等な関係を築くことができた。形式的な「結婚制度」にとらわれず、本質的な愛情と信頼で結ばれていたからこそ、それぞれの才能を最大限に発揮できたのよ。
夫婦別姓は「家族の絆を弱める」という反対意見があるけれど、それは間違いよ。本当の絆は、お互いの個性と自由を尊重し合うことから生まれる。女性が自分らしく生きることができる社会こそが、真に豊かな社会だと私は確信しているわ。
まとめ
三人のレジェンドのお話はいかがでしたか?それぞれの視点には深い愛情と知恵が込められていましたね。福沢諭吉の「独立自尊」、孔子の「仁義礼智」、ボーヴォワールの「個人の解放」—どの考え方も、大切なパートナーを思いやる気持ちから生まれています。この問題に「絶対的な正解」はありませんが、だからこそ当事者同士がじっくりと話し合い、お互いの気持ちを大切にできる選択をしていただければと思います。きっと、あなたたちらしい素敵な答えが見つかるはずです。
